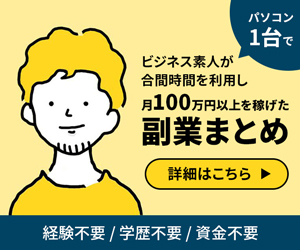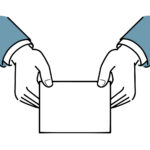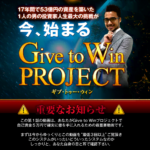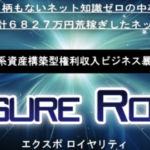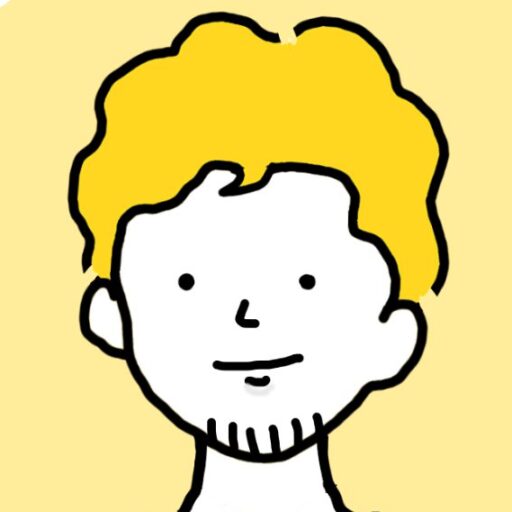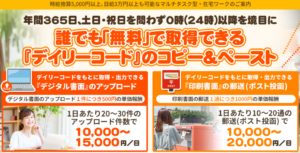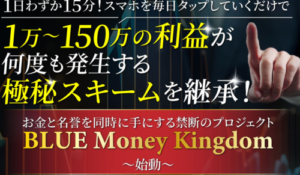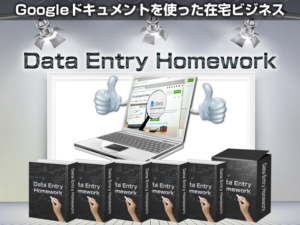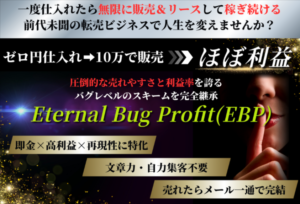「ジャストアンサーを利用したら高額な請求が来た…」そんなトラブルが相次いで報告されています。
専門家にオンラインで質問できる便利なサービス「JustAnswer(ジャストアンサー)」ですが、その料金体系が分かりにくく、多くの利用者が思わぬ請求トラブルに巻き込まれています。
本記事では、いわゆる「ジャストアンサー詐欺」と呼ばれる手口の実態と実際の被害例、返金対応の方法や消費者センターへの相談方法、そして未然に被害を防ぐための予防策までを詳しく解説します。
大切なお金を守るため、具体的で信頼性の高い情報に基づくアドバイスを提供しますので、ぜひ参考にしてください。
ジャストアンサーとはどんなサービス?
ジャストアンサー(JustAnswer)は、法律・医療・IT・ペットなど様々な分野の専門家にオンラインで相談・質問ができる定額制のQ&Aサービスです。
利用者はまずサイト上で質問したいカテゴリを選び、質問内容を入力すると、その分野の専門家から回答が得られるという仕組みです。
登録された専門家は資格保持者やプロの技術者などとされ、一般的な無料質問サイトより質の高い回答が得られることを売りにしています。
ジャストアンサーでは初回トライアル料金500円で質問を投稿できるキャンペーンを行っており、一見すると「500円で専門家に今すぐ相談」と宣伝されています。
しかし、実際にはトライアル期間(約7日間)の後、自動的に月額制の有料会員プランに移行し、月額約4,000~5,000円前後(ジャンルにより異なる)を継続請求される仕組みになっています。
例えば法律相談では月額5,980円、ペット相談は3,820円といった料金設定です。
このように便利なサービスである一方、料金体系が非常に分かりにくく不親切なため、「最初の1回だけのつもりが、その後毎月約5,000円がクレジットカードから引き落とされていた」という苦情が後を絶ちません。
こうした問題から、ジャストアンサーはネット上で「詐欺ではないか?」と疑問視される事態になっています。
ジャストアンサー詐欺と言われる理由(詐欺の手口)
ジャストアンサーのサイトでは「専門家が今すぐ500円で質問に回答」とうたってユーザーを誘導する。
しかしですが、「〜7日間のトライアルがたったの500円、その後は3,800円/月」という継続課金の条件が付いている。
この表示に気づかず契約し、高額の月額料金を請求されるケースが多発している。
ジャストアンサーが「詐欺まがい」と言われる最大の理由は、その料金請求の仕組みにあります。
利用者は質問を投稿しようとすると、まずクレジットカード情報の入力を求められます。
「500円で専門家が回答」という誘い文句につられてカード情報を入力し「トライアルをスタート」ボタンを押すと、その瞬間に有料会員(サブスクリプション)契約が自動成立する仕組みになっています。
画面上には小さな文字で「※トライアル終了後は自動的に月額〇〇円が課金されます」といった注意書きがあるものの、登録時には「無料で質問できる」と誤解させるような表記が目立つため、多くのユーザーが見落としてしまうのです。
さらに悪質な点は、質問の投稿前にシステムが自動応答で期待を持たせることです。
実際には質問を入力しても、送信ボタンが表示されずカード登録を促されます。
登録後はチャット形式でやりとりが始まりますが、最初に返ってくる回答はテンプレートの自動返信であり、あたかも専門家が即座に対応しているかのように装っています。
困って焦っている利用者ほど「すぐ答えてもらえるのかも」と信用して続行ボタンを押してしまい、そこで有料会員契約へ誘導されてしまう仕掛けです。
こうした「初回¥500」のトライアルでユーザーを釣り、実際には毎月数千円の定期課金契約を結ばせるビジネスモデルに対し、利用者からは「極めて不親切で悪質」「詐欺同然だ」との批判が噴出しています。
事実、米国カリフォルニア州ではジャストアンサー社が利用者へ無断で自動更新課金を行ったとして集団訴訟(クラスアクション)を起こされた事例もあります。
同訴訟では「サイト上で明確かつ目立つ説明なく利用者を月額課金プランに登録し、本人の明示的同意を得ていない」という点が問題視されました。
つまり日本国内だけでなく海外においてもジャストアンサーの手法は法的に疑問視されているのです。
まとめると、ジャストアンサー詐欺の手口は以下のようになります。
「500円で質問できる」と宣伝し、困っている利用者の気を引く、質問入力後にクレジットカード登録を要求し、登録すると即有料会員契約に移行。
トライアル終了後は自動で月額3,000~5,000円前後の料金を課金(表示がわかりづらく多くの人が認識せず)
解約手続きが分かりにくく煩雑で、放置すると延々課金される。
実際には回答が得られなかったり質が低かったりするケースもあるが、質問を見るために課金だけは発生する。
以上のように、「完全な詐欺」と断言はできないものの、利用者に極めて誤解を招きやすい仕組みであることは確かです。
次章では、こうした手口によって実際に生じている被害事例を見てみましょう。
実際に報告された被害事例
ジャストアンサーに関する請求トラブルは日本全国で多数報告されており、消費生活センターにも相談が寄せられるほど社会問題化しています。
例えば2022年には国民生活センター(消費者庁所管)に「パソコンの不具合解決のために500円の質問サイト(ジャストアンサー)を一度利用しただけなのに、後日勝手に5,000円がクレジットカードから引き落とされた。返金してもらえないか」という相談が寄せられました。
センターは「それはサブスクリプション契約になっている可能性がある。申込み画面やメールを確認し、不要なら事業者の指示に従って速やかに解約すること。
返金は規約に基づく対応になるため必ずしも認められない」と注意喚起しています。
このように、公的機関も「解約したはず」「契約してない」と思い込んでいる利用者が非常に多い現状を踏まえて警鐘を鳴らしているのです。
実際の被害ケースとして、ネット上には次のような体験談が数多く挙がっています。
ケース①
「深夜にスマホが壊れ、検索上位に出てきたサイトを携帯会社公式のサポートと勘違いしてジャストアンサーに相談してしまった。
回答が来ないまま不審に思い、翌朝カード会社に連絡すると既に500円+質問料として数千円が請求されていた。
消費者センターと警察署に相談し、カードを停止するよう助言された」という例。
※この利用者は焦っていたためサイトの表示を誤認したと語っています。
ケース②
「500円の支払いに同意して法律相談を投稿したが、一晩待っても回答が来ない。不安になって調べたらジャストアンサーの口コミで初めて事態を把握。
慌てて登録を解除したが、念のため今後数ヶ月はクレジット明細をチェックする必要があると痛感した」との声。
※幸い500円だけで済んだが、「良い勉強代になった」としています。
ケース③
「トライアル後に自動的に定額会員プランに移行するとは知らず、クレジットカード明細をよく確認していなかったため、気付いた時には月額4,500円が7ヶ月間も引き落とされていた」という深刻な被害報告もあります。
7ヶ月分で合計3万円以上にもなり、大きな損失です。
ケース④
「ジャストアンサーに11月に一度質問してすぐ解約したというメールが届き安心していたが、翌月もその次の月も引き落としが続いた。
電話問い合わせすると『お客様は既に解約済み』との自動音声で埒が明かず、メール送信もできない。
警察に相談したが『現状できることはない』と取り合ってもらえなかった。このまま請求され続けるのか不安」という声もありました。解約したつもりでも処理がされておらず、途方に暮れているケースです。
ケース⑤
Yahoo!知恵袋上には「ジャストアンサーから身に覚えのない請求が来た。
一定期間で解約しないと自動的に定額会員になるとのこと。返金できた方はいますか?方法を教えてください」という質問も投稿されています。
回答者からは「詐欺グループです。自分も引っかかったので警察本部と消費者センターに相談した」といった過激な意見も寄せられており、被害者の怒りと不安の大きさがうかがえます。
ケース⑥
ジャストアンサー被害についてまとめた個人ブログには、「母がジャストアンサーに騙されそうになったが、幸い被害額は1円もなかった。
だが同様の被害報告が相次いでおり非常に悪名高いサイトだ」との証言が掲載されています。
コメント欄にも「自分も毎月3,400円を1年間も抜かれて約4万円の被害。消費者センターに相談し、紹介された番号に電話したが担当は取り合わない態度だった。しかし消費者センターの名前を出した途端態度が変わり、解約できた。7日以内に解約すべき特約を見落としたと言われたが、全く身に覚えがなく頭にきた」という体験談が寄せられています。
このように、消費生活センターや警察に相談した途端に対応が変わったという声もあり、事業者側もクレームの多さを認識している様子がうかがえます。
以上の事例から、ジャストアンサーでは「知らない間に定額課金されていた」「解約したと思ったのに請求が止まらない」といった被害が後を絶たないことが分かります。
消費者からの苦情が非常に多いため、消費生活センターの担当者ですらジャストアンサーの名前を聞けば状況を把握できるほど有名なトラブルになっているとの指摘もあります。
では、もし自分がこうした請求被害に遭ってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
次の章で具体的な対処法を説明します。
請求トラブルが起きた場合の対処法(解約・返金の方法)
もし「ジャストアンサーで質問してしまった」「身に覚えのない請求が来て困っている」という場合は、以下の手順で迅速に対処しましょう。
1. すぐに有料会員を解約する
まず第一に、ジャストアンサーの有料会員プログラムを速やかに解約してください。解約しない限り契約は自動更新され、月額料金の請求が続いてしまいます。
解約手続きはウェブ上の「マイアカウント」から行うことができますが、サイトの操作に不安がある場合や手続きがうまくいかない場合は電話での解約連絡が確実です。
ジャストアンサーのカスタマーサポートに直接電話する場合は、「0120-974-951」(平日9:00~18:00)に連絡しましょう。
この番号はジャストアンサーの日本語サポート窓口で、海外本社(米カリフォルニア州)に転送されることもありますが、日本語で解約の旨を伝えれば対応してもらえます。また、一部情報では「0120-952-598」という番号も案内されています。
繋がりにくい場合は時間をおいて再度かけ直すなどしてみてください。解約の際は、「今後一切課金しないようにしたい」旨をはっきり伝えましょう。
念のため、解約手続き完了のメールを送ってもらうか確認し、記録を残しておくことをお勧めします。
電話で解約した場合も、日時・担当者名をメモするか通話を録音しておくと安心です。
2. クレジットカードを一時停止する(必要に応じて)
カード情報を入力してしまった以上、解約手続きが完了するまで追加の請求が発生する可能性があります。
不安な場合は、クレジットカード会社に連絡してカードを一時停止(利用停止)することも検討してください。
実際、先述の被害者もカード会社から「とりあえずカードを止めるように」と指示されています。
カードを停止すればそれ以上の引き落としは防げますが、既に発生した請求については別途対応が必要です。
カード会社に事情を伝えて支払いの差し止めやチャージバック(不当請求の取消)が可能か相談することも有効です。
ただし、ジャストアンサーの場合利用者自身がウェブ上で支払いに同意している形になっているため、カード会社による返金対応は難しいケースもあります。
そのため、カード停止はあくまで追加被害を防ぐ緊急措置と考え、根本的な解決は次項の返金交渉で図りましょう。
3. 返金を求める交渉をする
解約手続きが済んだら、可能であれば既に支払った料金の返金交渉を行います。ジャストアンサーの利用規約上、基本的に支払済み料金の返金は認められないことになっています。
しかし、初回トライアルのみの利用で継続利用していない場合や、課金システムの不明瞭さに起因するトラブルであることを主張すれば、返金に応じてもらえる可能性もあります。
実際、ジャストアンサーの内部で専門家として活動する人物からは「解約は簡単にでき、30日以内であればほとんどの場合返金対応してもらえる」との証言もあります。
そのため、請求発生から日が浅い(1ヶ月以内)場合は諦めずに返金要求をしてみる価値があります。 返金交渉のポイントは以下の通りです。
カスタマーサポートに連絡し、「継続課金とは知らなかった」「サービスを利用していないので返金して欲しい」と丁寧に伝える。
可能であれば解約手続き前に「返金してもらえるか確認したい」と問い合わせるのが望ましい、とのアドバイスもあります。解約後よりも解約前の方が交渉しやすい場合があるためです。
最初の請求以降利用していないことを強調し、「事前説明が不十分で誤認した」「500円だけのつもりだった」と自分の状況を具体的に説明する。
サポート担当者が渋る場合は「消費生活センターにも相談済みである」ことをほのめかすのも効果的です。
消費者センターから苦情が来ることを事業者は嫌がるため、態度が軟化するケースがあります。
実際に「消費者センターに通報すると伝えたら返金対応してもらえた」という報告もあります。
上記のように交渉しても事業者側が返金を拒否する場合や、「利用開始からかなり経っているので返金は難しい」と言われた場合もあるでしょう。
その際は、次に説明する消費生活センター等の公的機関に相談し、第三者の力を借りることを検討してください。
まとめ
ジャストアンサーは一見便利なサービスですが、その料金体系の不透明さから結果的に「詐欺だ」と感じる利用者が多いのが現状です。
初回500円の誘い文句と自動更新のカラクリによって高額な課金トラブルが多発しており、事前説明の不足や解約手続きの煩雑さが大きな問題点とされています。
利用する際は十分に注意し、安易な登録は避けましょう。
万が一「ジャストアンサー詐欺」に遭ってしまった場合でも、適切に対処すれば被害を食い止めたり返金を受けられる可能性もあります。
すぐに有料会員を解約し、必要に応じてカードを停止、そして消費生活センターなど公的機関へ相談してください。
泣き寝入りする必要はありません。