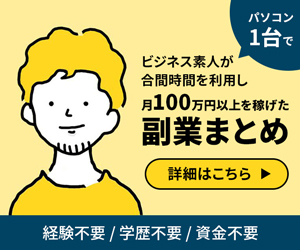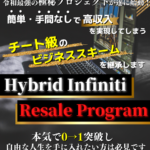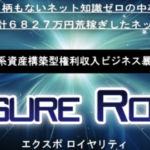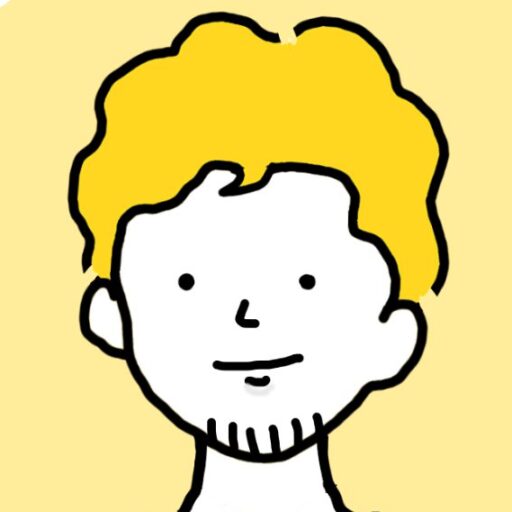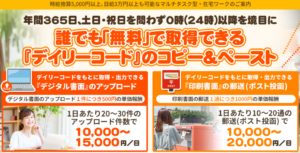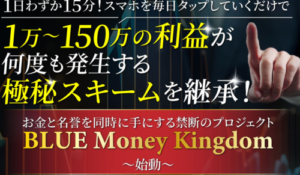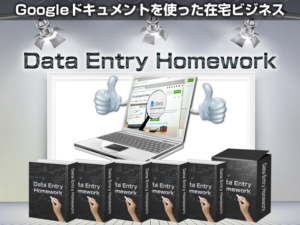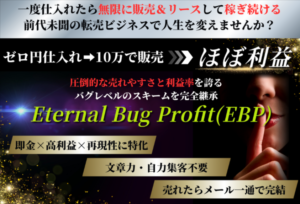最近、「Quantum AI」や「Quantum AI Elite」という名前の投資プラットフォームがSNSやネット広告で話題になっています。
著名人の名前を出した広告や「AIで自動で儲かる」といった謳い文句に興味を持つ初心者もいるかもしれません。
しかし、その口コミを見ると「怪しい」「詐欺ではないか」といった声も少なくありません。
本記事では、Quantum AIとは何か、そのサービス内容から、Quantum AI Eliteとの関係、さらには日本語で確認できる口コミ・評判まで徹底的に調査し、その「怪しさ」の理由を解説します。
加えて、類似サービスとの比較や、投資初心者・仮想通貨ユーザーが注意すべきリスクについてもまとめます。
誇張表現を避け、公式情報や専門サイトの情報をもとに中立的な視点でお伝えします。
Quantum AIとは何か?その概要とサービス内容
Quantum AIは、一見すると最先端の技術を活用した投資サービスのように宣伝されています。
広告などによれば、「AI(人工知能)を搭載した自動取引プラットフォーム」であり、暗号資産(仮想通貨)の売買を自動で行い、高精度のトレードで利益を生み出すとうたっています。
実際、Quantum AIは“成功率90%”とも称され、10回の取引のうち9回は勝てると主張しているとの情報もあります。
初心者でも暗号資産の知識がなくても簡単に利益を狙える、「今すぐお金持ちになりたい人にとって100%完璧なソリューション」といった宣伝文句も確認されています。
しかし、このような高い勝率や簡単に稼げるという主張には注意が必要です。
後述するように、Quantum AIは金融当局の規制を受けておらず、サービスの正当性や実績を裏付ける客観的な情報が極めて不足しています。
公式サイト上でも運営会社や所在地、連絡先といった基本情報が公開されておらず、その透明性には大きな疑問が残ります。
要するに、Quantum AIは「高度な自動取引技術」を謳っているものの、その中身(アルゴリズムや運用実績)は不明であり、実態がよくわからないサービスだと言えます。
また、名前から連想される「量子コンピュータ×AI」という先端技術との関連性も不透明です。
確かに学術分野には「量子AI(Quantum Artificial Intelligence)」という研究領域がありますが、Quantum AIというプラットフォームはそのような先端技術とは無関係であり、あくまで名称に過ぎないと指摘されています。
Googleが進める「Quantum AI」プロジェクト(量子コンピューティングの研究開発)とも一切関係がありません
Quantum AI Eliteとは何か?Quantum AIとの関係
Quantum AI Elite(クアンタムAIエリート)は、Quantum AIと非常に似た名前を持つ関連サービスです。
日本国内では主にこちらの名前で広告が出回っており、実態はQuantum AIと同様の仮想通貨自動売買ツールとされています。
要は、Quantum AI EliteはQuantum AIの派生版あるいはリブランドと考えられ、基本的な仕組みや提供内容は変わらない可能性が高いです。
Quantum AI Eliteが注目を集めた一因に、著名人・有名人の名前を利用した広告宣伝があります。
例えば、日本のSNS上で確認された広告では、掲示板サイト「2ちゃんねる」創設者であるひろゆき氏(西村博之氏)が、Quantum AI Eliteを愛用しているかのような内容が表示されていました。
さらに、「ひろゆき氏が生放送中にQuantum AI Eliteの存在をうっかり暴露し、日本銀行に提訴された」というショッキングな偽ニュースまで作られていました。
一見すると「日本政府が隠してきた極秘の投資プラットフォーム」を匂わせるような話ですが、これは完全なデタラメです。
実際にはひろゆき氏とQuantum AI Eliteに何の関係もありませんし、日本銀行が提訴した事実もありません。
これらは巧妙に作られたフェイクニュース広告であり、ニュースサイトの記事を装ってユーザーを騙そうとする手口です。
Quantum AI Eliteという名称自体、海外で以前から問題視されていた「Quantum AI」というプラットフォームと名前を変えただけの可能性が指摘されています。
海外版のQuantum AIでは、イーロン・マスク氏など著名な起業家の名前や写真を無断使用したフェイク広告が多数確認されており、各国の金融当局から警告も出ているほどです。
Quantum AI Eliteもそれと共通点が多いため、実態はQuantum AIと同一で名前だけ変えたものと考えるのが自然でしょう。
以上のように、Quantum AI EliteはQuantum AIと本質的に同じものであり、宣伝のために著名人を利用した悪質なマーケティングが行われている点に大きな特徴があります。
次章では、実際に利用者やネット上でどのような口コミ・評判が出ているのかを見てみましょう。
Quantum AIの口コミ・評判
Quantum AIおよびQuantum AI Eliteに関する日本語の口コミや評判を調査したところ、ほとんどが否定的・警戒的な内容でした。
SNS(X/旧Twitter)、ブログ、レビューサイト、Yahoo知恵袋のQ&A、YouTubeなど様々な媒体で、多くのユーザーが注意喚起を行っています。
SNSやブログでの口コミ
まず、SNSや個人ブログ上の声として多かったのは「詐欺サイトだ」「こんなのでお金持ちにはなれない」という指摘です。
実際に登録したとみられる人の投稿では、「Quantum AI Eliteに登録後、異なる電話番号から何度も勧誘の電話がかかってくる」という具体的な体験談がありました。
しかも毎回電話番号が変わるため、「こんなことをするまともな会社はあり得ない」と不信感を募らせています。
また、Quantum AI Eliteに関する広告がGoogleニュースやgooニュース、読売新聞のサイトに偽装されて表示されていたという報告もあります。
一見すると大手ニュースサイトの記事のように見えるため「正直かなりの人が引っかかるだろう」という声もありました。
これらは前述の通りフェイクニュース広告であり、著名人やニュース媒体の権威を騙って信用させようとする典型的な手口です。
SNS上では他にも「Quantum AI Eliteという詐欺が流行っているらしい。皆さん引っかからないように!」という注意喚起の投稿も確認できます。
この投稿者は「こんなのでお金持ちにはなれません。
日銀から電話とか提訴って設定に無理がある」と、先述の荒唐無稽な広告内容にツッコミを入れつつ警鐘を鳴らしていました。
Q&Aサイトでの評価
Yahoo!知恵袋でもQuantum AIに関する質問が複数寄せられており、回答者の多くは「詐欺です」と断言しています。
その一例として、「楽天の三木谷社長が宣伝しているQuantum AIって詐欺ですか?」という質問に対し、あるカテゴリマスター(上級回答者)は「詐欺です。ちなみに三木谷社長の写真は勝手に使用されています。他にも有名実業家たちの名前や画像が勝手に使われています」と明言しています。
この回答が示すように、Quantum AI関連の宣伝には楽天グループ社長の三木谷浩史氏をはじめ、孫正義氏(ソフトバンク)、前澤友作氏(元ZOZO社長)、タモリ氏(タレント)など数多くの著名人が無断で登場させられており、「そんな大物が推すなら安心かも」と思わせる罠になっているのです。
別のQ&Aでは「YouTube広告によくイーロン・マスク氏が出てきてQuantum Open AIを勧めているが本当か?」という趣旨の質問があり、ベストアンサーでは「海外の詐欺グループによる典型的な詐欺だ」と断定されていました。
回答者は「具体的にはソフトバンク孫氏、楽天三木谷氏、ZOZO前澤氏、トヨタ豊田章男氏…様々な有名人の名前がコピペで使われている」と指摘し、公式サイトらしきページも存在するが全て嘘であると注意喚起しています。
このように、Q&AサイトでもQuantum AI/Eliteは「有名人を騙った儲け話=詐欺」という認識が広がっていることがわかります。
レビューサイト・専門メディアでの評価
投資系のレビューサイトや専門メディアでも、Quantum AIに対する評価は極めて厳しいものがあります。
たとえばBrokersViewという海外ブローカー情報サイトでは、Quantum AIを「規制されていない取引プラットフォーム」と位置づけた上で、「Quantum AIはどの金融当局からも規制を受けておらず、投資家の資金を預けるのは非常に危険。Quantum AIは詐欺のようだ」と結論づけています。
実際、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)はQuantum AIに関して公式警告を発しており、新たな関連ウェブサイトが次々現れていることにも言及しています。
さらにQuantum AIは「英国に本拠を置く」と主張しつつ英国の金融行為監督機構(FCA)に登録されていないことも確認されており、国際的にも信頼性が否定されている状況です。
日本の法律事務所系サイトでも、Quantum AIに関する相談事例が紹介されています。
とある調査記事では「Quantum AIは詐欺の可能性が高い危険なサイト」であり、「出金できない」「手数料を請求される」といった被害報告が多数あると述べられています。
実際、「出金しようとすると『税金や手数料を先に払え』と言われた」「サポートと連絡が取れなくなり出金不能になった」「画面上では利益が増えているのに引き出せない」といった典型的な被害パターンがまとめられていました。
これらは後述する「怪しいと言われる理由」に詳しく挙げますが、要するにQuantum AI(Elite)は登録・入金しても出金できない可能性が極めて高く、実質的に利用者が利益を得たという信頼できる声は皆無というのが、現時点での口コミの総意と言えるでしょう。
Quantum AIが「怪しい」「詐欺では?」と言われる理由
前章までで見てきた口コミや評価から、Quantum AI(およびQuantum AI Elite)が「怪しい」「詐欺ではないか」と言われる主な理由を整理してみます。以下に具体的なポイントを挙げ、その根拠を説明します。
運営会社や連絡先など基本情報が不明
Quantum AIの公式サイトや関連ページには、通常サービス提供者が公開すべき運営会社名、所在地、責任者、連絡先などの情報がほとんど掲載されていません。
日本版サイトには「私たちに関しては」という会社案内ページが存在するものの、社名や企業実績、所在地や電話番号といった記載は一切見当たりません。
唯一それらしき情報として「Anton Kovačić」という人物名が代表者のように記載されていますが、調査によればこの名前は他の多数の取引プラットフォームでも使い回されているもので、真の創設者とは言い難い状況です。
実態の見えないサービスほど信用できないものはありませんが、Quantum AIはまさにその典型であり、この不透明さ自体が大きなリスク要因です。
さらに技術的な面でも不審点があります。
CyberGuard社の調査によれば、Quantum AI Eliteのドメイン(サイトURL)は作成されたばかりで、Whois情報(ドメイン登録者情報)は完全に匿名化されているとのことです。
つまりサイト開設者の情報は隠されており、運営元の実態が全く掴めません。信頼できる正規の金融サービスであれば、少なくとも公式サイト上に会社情報が記載されていたり、長期間運用されていた実績があったりするものですが、Quantum AI/Eliteにはそれが見当たらないのです。
このように運営の実体が見えない点だけでも十分「怪しい」と言わざるを得ません。
金融ライセンス未取得・無登録業者である
信頼できる投資サービスかどうかを判断する基準の一つに、その事業者が金融当局のライセンス(認可)を受けているかがあります。
日本国内で暗号資産取引サービスを提供するには金融庁への登録が必要ですが、Quantum AI/Eliteは日本の金融庁ライセンスを保持していません。
海外業者であれば所在国のライセンスが必要ですが、前述の通りQuantum AIは英国拠点と称しつつFCA(英国金融行為監督機構)にも未登録であり、主要国いずれの規制当局からも認可を受けていない無登録業者です。
各国の金融規制当局もQuantum AIに対する警戒を強めています。
例えばドイツのBaFin(金融監督庁)は2025年3月にQuantum AIに対する公式な警告を発し、Quantum AIが必要な認可を受けずに違法な金融サービスを提供している疑いを公表しました。
またイタリアやオーストラリアなど他国でも、同様にQuantum AIに関する注意喚起が出されています。
いかなる国でも規制を受けていないプラットフォームにお金を預けることは非常に危険であり、法的保護も全く期待できません。
このような無許可営業の時点で、Quantum AIが正規のサービスとは程遠い存在であることは明白です。
著名人の名を騙ったフェイク広告を多用
Quantum AI/Eliteが「怪しい」と言われる大きな理由の一つが、その宣伝手法の悪質さです。前述のとおり、ひろゆき氏やイーロン・マスク氏をはじめ、多数の有名人がQuantum AI関連の広告で無断使用されています。
例えば海外向けには「Quantum AI (Quantum Open AI)」の宣伝にイーロン・マスク氏の写真が掲載されていましたが、当然ながら本人は全く無関係です。
日本向けにはタレントのタモリ氏や実業家の孫正義氏・前澤友作氏などが「稼げるAI投資ツールを紹介した」とする偽ニュースに登場させられたケースも報告されています。
いずれも信頼性を偽装するためのフェイクニュースであり、「著名人がお墨付きを与えている」という印象操作で利用者を勧誘する古典的な詐欺の手口です。
一般的に、本当に優れた投資サービスであればフェイクニュースに頼る必要はありません。口コミで評判が広がったり、正式なプレスリリースや提携発表が行われるはずです。
Quantum AIの場合、そのような正規の露出は皆無で、代わりに虚偽の広告ばかりが目立つこと自体、信用できない証拠と言えるでしょう。
出金トラブルなど利用者被害の報告
実際にQuantum AI/Eliteを利用した(または試みた)人々からは、出金ができないという切実な被害報告が多く上がっています。
具体的な例として、「入金後に出金申請をすると『システムエラー』や『税金・手数料を支払う必要がある』などと理由をつけられて引き出せない」という体験談が複数確認されています。
中には、「画面上では利益が増えていくが、実際に出金しようとするとあれこれ言われて一切引き出せなかった」という証言もあります。
これは詐欺的な投資サイトの典型的な手口で、ユーザーに利益が出ていると思わせ追加投資を促しつつ、最終的には出金拒否して資金を巻き上げるものです。
また、勧誘の電話やメールがしつこく来ることも被害報告として挙げられます。
最初は日本語で電話が来るものの、話している人は片言の場合もあり、海外のコールセンターから掛けてきている様子だという証言もありました。
番号を変えて何度も連絡してくるなど常軌を逸した対応から、「明らかにまともな会社ではない」と感じたユーザーも多いようです。
このように、実際に利用しようとした人からのリアルな声がいずれも酷い内容であることは、Quantum AI/Eliteが信頼できないサービスである根拠となります。
「利益どころか元本すら戻ってこない」「個人情報を渡すと悪用されるリスクがある」といった指摘もあり、これらが事実であれば極めて悪質です。
金融サービスとして最低限の信頼性すら確保できていないため、「怪しい」と言われるのは当然でしょう。
AIの実績やロジックが公開されていない
最後に技術面の不審点として、Quantum AI/Eliteが売りにしている「AIによる自動取引のロジック」や「運用実績」について一切公開されていないことが挙げられます。
もし本当に画期的なAIアルゴリズムで高勝率を実現しているのであれば、その概要や過去のパフォーマンスデータ等が提示されても良いはずですが、公式にはそうした情報は見当たりません。
一般論として、「AIを使っているから儲かる」というのは短絡的な考えであり、AI=必勝ではありません。
市場には様々な自動売買ツールがありますが、どんな高度なAIでも100%利益を保証することは不可能です。
にもかかわらずQuantum AIはその仕組みを秘密のまま、「AI搭載」「高精度」といったキャッチコピーだけで人を集めようとしている点が不透明です。
以上の理由から、Quantum AIおよびQuantum AI Eliteは非常に信頼性が低く、投資詐欺まがいの危険なプラットフォームであると判断できます。
実際、調査を総合すると「ほぼ詐欺確定」と言ってよい状況であり、とてもおすすめできるものではありません。
類似サービスとの比較:よくある詐欺的投資ツール
Quantum AI以外にも、世間には今回と似たような自動売買ツール型の投資話が存在します。
その多くが今回と同様に著名人の名前を騙った広告でユーザーを誘い、初期入金をさせて資金を引き出せなくするという手口です。
過去に報告された名前としては、例えば「Immediate X AI」や「BTC+11 LEXIPRO」といったものがあり、いずれも名前こそ違えど同種の投資プラットフォームへの勧誘でした。
これらもQuantum AI同様に「高精度AIで自動取引」「短期間で◯◯万円稼げた」などと宣伝されましたが、調べてみるとやはり詐欺疑惑が濃厚とされています。
実際、Immediate X AIについては有志の調査ブログで「海外の詐欺グループによる典型的な詐欺で、絶対に登録してはいけない」と強く警告されていました。
また、「Quantum Apex AI」という名称のサービスも確認されています。こちらも内容はQuantum AIと酷似しており、ファーストリテイリングの柳井正氏(ユニクロ創業者)などの引用を装った広告テキストが使われていたことがYahoo知恵袋で報告されています。
回答者は「かなりの被害者を出している海外詐欺グループによるもの」と断定しており、具体的な関連ページへのリンクを挙げて注意を促していました。
さらに、今回名前が挙がったQuantum Open AIも類似のものです。これはQuantum AIの亜種のような名前ですが、前述の通りイーロン・マスク氏を引き合いに出した宣伝が確認されています。
日本国内では「Bitcoin 360 AI」という名前で前澤友作氏の写真が使われた事例もありました。
いずれにせよ、手口や内容に大差はなく、名前を変えながら次々と現れているのが実情です。
比較すると、Quantum AI/Eliteだけが特別に悪質というより、これら一連の自動売買ツール詐欺の代表格がQuantum AIだと言えるでしょう。
共通する特徴は以下の通りです。
有名人やニュースサイトを装ったフェイク広告で勧誘する
「AI」「自動取引」「高勝率」など最新技術や魅力的なワードを強調する。
初回入金をさせた後は出金させない(エラーや追加手数料要求など理由をつける)
運営会社や所在地が不明で突然サイト閉鎖しても追跡困難
このような類似サービスは、名前や表向きのストーリーを変えながら登場と消滅を繰り返しています。
被害に遭わないためには、「新しい儲け話だけど本当に大丈夫か?」と常に疑う姿勢が大切です。
ひとつでも怪しい点があれば手を出さないことが、自己防衛の観点で非常に重要になります。
投資初心者・仮想通貨ユーザーにとってのリスクと注意点
最後に、Quantum AI/Eliteのような案件から身を守るために、投資初心者や暗号資産ユーザーが心に留めておくべきリスクと注意点をまとめます。
「必ず儲かる話」は疑ってかかる
「1週間で◯◯円儲かった」「成功率90%」などの謳い文句は魅力的に聞こえますが、投資の世界で絶対に儲かる保証はありません。異常に高い利益や勝率をうたうものは高確率で詐欺です。
冷静に考えて、リスク無しに簡単にお金を増やせるなら皆がすでに富裕層になっているはずです。甘い言葉には決して惑わされないようにしましょう。
公式ライセンスと実績を確認する
投資プラットフォームを利用する際は、そのサービスが金融庁など信頼できる機関に登録・認可されているかを必ず確認しましょう。無登録業者は法律違反であり、トラブルが起きても保護されません。
また過去の利用者からの評判(第三者のレビューや評価)もチェックし、出金拒否などの苦情がないか調べることが重要です。
個人情報の取り扱いに注意
怪しいサイトに氏名・住所・電話番号・クレジットカード情報などを登録してしまうと、個人情報を悪用されるリスクがあります。
実際、Quantum AI Eliteでは登録直後から海外の不審な番号から電話が頻繁にかかってくるケースが報告されています。
不必要に個人情報を渡さない、怪しい相手からの連絡は無視するなど、自分の情報を守る意識を持ってください。
暗号資産での送金は特に慎重に
仮想通貨での入金を要求される場合、それは送金後の追跡や返金が非常に難しいことを意味します。
ブロックチェーン上の取引は基本的に取り消せません。
詐欺業者は銀行振込より暗号資産を好む傾向があります。理由は足がつきにくく、被害者が取り戻しにくいからです。
暗号資産での支払いを急かされたら警戒度を最大にしてください。
まとめ
本記事ではQuantum AIおよびQuantum AI Eliteについて、その概要から口コミ・評判、そして「怪しい」と言われる理由や注意点まで詳しく解説しました。
調査の結果、Quantum AI/Eliteは信頼性に乏しく、詐欺的な疑いが非常に強い投資プラットフォームであることがわかりました。
著名人を利用した広告や「AIで楽々稼げる」といううたい文句は全て誇張・虚偽であり、信じるに値しません。
もし登録・入金してしまった場合、利益どころか元本すら戻らない可能性が高く、大変危険です。
幸い、ネット上の口コミ・評判を調べれば悪い噂ばかりであることから、多くのユーザーが警戒心を持っている状況です。
投資初心者や副業を探している方にとって、Quantum AIのような話は非常に魅力的に映るかもしれません。
しかし、「うまい話には裏がある」という言葉通り、今回のケースは典型的な詐欺の手口に当てはまります。
どうか十分にリスクを認識し、安易に飛びつかないようご注意ください。
最後に、仮に同様の怪しい案件に出くわした場合は、決して焦ってお金を振り込まず、本記事で述べたポイントを思い出して慎重に対応してください。
大切な資金と個人情報を守るために、冷静な判断と情報収集を常に心がけましょう。それが、投資で失敗しないための第一歩です。